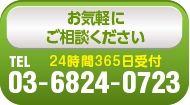日本の読者の皆様へ 2017年12月30日 ノーム・チョムスキー
「誰が世界を支配しているのか?」
1939年に第二次世界大戦が勃発したとき、米国の外交問題評議会は「戦争平和研究会」を設立しています。
国務省高官の参加を得て、戦後の世界秩序を立案したのです。
この研究会は1945年に戦争が終る頃に政策を提案しましたが、その内容は学術の領域を超えています。
戦後すぐに国務省政策企画部の文書が発表されましたが、戦争中の研究と、考え方も表現もよく似ています。
当時の国務省の政策企画部のトップは、著名な政治家ジョージ・ケナンでした。
このときに示された政策は、その後、状況に合わせた修正はありましたが、おおむね忠実に実施されています。
「戦争平和研究会」は、太平洋戦争における米国の勝利を確信していました。
また、西欧の連合国に対しても米国が圧倒的な力を持つとみていました。
しかし、ソ連対ドイツの勝敗には、確信を持てませんでした。
研究会は当初、ドイツが勝つと予測しており、米独二カ国による世界支配を計画していました。
米国が「大領域(グランドエリア)」と呼ぶ地域を支配し、残りをドイツが支配する世界です。
「大領域」には少なくとも西半球、極東、旧大英帝国領が含まれていました。
1943年のスターリングラード攻防戦、クルスク大戦車戦のあと、ソ連がナチス・ドイツを破ることがはっきりし、「大領域」の計画も変更されました。
新たな「大領域」には西ヨーロッパとその工業中心地が加わり、さらに可能な限り広げることになったのです、、、
戦後の世界体制においては、米国が「絶対的な力」を持たなければならない、と研究会のメンバーたち
は認識していました。
米国の世界経営に介入しようとする国家の「主権行使を制限する」ためです。
そこで「大領域」において「米国が軍事・経済面で圧倒的優位を維持できる総合政策」を考案したのです。
終戦から数年後、ケナンは重要な政府資料(PPS/23, 1948)で世界情勢を検討しています。
https://library.schlagergroup.com/chapter/9781961844179-book-part-178
George F. Kennan: “PPS/23: Review of Current Trends in U.S. Foreign Policy”
彼は当然、西ヨーロッパの情勢について多くを語っていますが、グローバル・サウス(南半球の発展途上諸国)にも軽く触れています。
西欧の同盟国は「アフリカ大陸の植民地や属領の経済発展と搾取に取り組める」と助言しています。
ラテンアメリカについては、米国大使たちとの会合で、実利的な関心に従え、と述べています。
それは、たまたま他国にある「われわれの資源を守るため」です。
そこでケナンは
「現地の警察による抑圧を見てもためらってはならない。これは恥ずべきことではない。
なぜなら共産主義者たちは国家への反逆者だからだ、、、
強権を持つ政権のほうがリベラルな政府よりも望ましい。
自由な政府は寛大でノンビリしていて共産主義者が浸透するかもしれない」
と述べています。
誰が共産主義者なのかは、極めて幅広く理解されることになりました。
アジアに関して、ケナンは次のように語りました。
「米国は世界の富の50%を所有するが、人口では6・3%しか占めていない。この格差は特に米国とアジアの間で顕著だ。
この状態では必ず妬みと怒りの対象となる。
これから必要なのは、特別な関係を工夫して格差を維持し、米国の安全保障を保つことだ。
私たちは目の前の国家目標に集中しなければならない。
利他主義や世界への善行などの”贅沢”は、現在とてもできない、、、
極東では、人権とか生活水準の向上とか民主化などという”非現実的”な話をやめるべきだ。
力の論理で交渉しなければならない時代が、すぐにやって来る。
理想主義のスローガンに邪魔されることは、少なければ少ないほどよい」
中東では英国の支援を期待していました。
アフリカはヨーロッパ再建のために「搾取」されることとなり、東南アジアの「主な機能は日本や西ヨーロッパへの資源供給地である」とされています。
工業社会は再建されることになりましたが、理由は地政学的な配慮と戦争で発生した「ドル不足」を克服するためでした。
ヨーロッパはドル不足で米国の巨大な余剰製造物・農産物を購入できなかったのです。
これは深刻な問題でした。
なぜなら、大市場や投資の機会、国家による巨大な国内投資がなければ、米国は戦時景気で脱出したばかりの大恐慌に、再び落ち込むかもしれなかったからです。
「ドル不足」は三角貿易で乗り越えることになりました。
米国が資源を元植民地から購入し、利益は昔のヨーロッパの支配者の懐に入り、彼らが米国の輸出品を購入するわけです。
これならば米国は戦争中に蓄えた余剰資金を投資するチャンスも得られます。
この「大領域」は開放的なグローバル制度で、投資家たちと成長を始めた多国籍企業には自由が与えられました。
「対等な立場」での競争ならば、米国企業が勝利を納めるのが当然だと思われていました。
なぜなら、背後に米国のパワーがあるからです。
このような論理は一世紀前の英国を思わせます。
当時の英国は競争相手よりも資本が豊富となり、自由貿易を歓迎しています。
ただしその「自由」は、多くの制約を伴う一時的な策で、海外の競争相手に勝てなくなると破棄されました。
このときの主な競争相手は日本でした。
これが第二次世界大戦における太平洋戦争の重要な背景となっています。
現在の米国が提唱する”開放的なグローバル制度”もよく似ています。
この「開放的なグローバル制度」の意味は、1944年に米国務省の「米国の石油政策」という文書で明確にされています。
その文書では、次のように主張しています。
「(西半球における)現在の絶対優位の立場を維持しなければいけない。用心深く米国の特権を保護すると同時に、新しい地域では、米国企業にとって機会均等となる”門戸開放”の原則を強調すべきだ」
つまり、すでに持っているものについては扉を閉じて他国に渡さず、まだ持っていないものは「門戸開放」の原則に従って、奪うという考えです。
米国の国内経済においても理屈は似ています。
米国で自由貿易をもっとも熱心に主張するグループは、困難に直面したときは救済措置を求めて、低姿勢で米国という過保護国家に助けを求めます。
米国務省による石油政策は実施され、英国は呆然としました。
それまで中東の石油生産は英国が支配していたのですが、「米国の国内石油産業は保護される一方、
海外にあった英国の石油生産は開放され、強力な米国の国際石油資本との競争を余儀なくされた」
のです(石油産業の専門家デヴィッド・ペインター)。
フランスの利権はもっと簡単に否定されました。
ドイツに占領されていたフランスは敵国とみなされ、権利を剥奪されたのです。
「大領域」内にある中東の巨大なエネルギー資源は、米国にとって特に重要ではありませんでした。
米国は長年にわたって世界の主要な石油産出国だったからです(現在、再びその立場に戻りそうです)。
しかし、中東の石油は世界支配の手段として重要でした。
「大領域」の工業中心地は米国の影響で石油に頼るようになり、ヨーロッパを復興させたマーシャルプランの援助金の多くも石油購入にあてられています。
利潤を別にしても、米国は石油資源を支配することで、同盟国への「拒否権」を持つことになったと、ジョージ・ケナンは説明しています。
彼は特に日本について述べているのです。
当時、日本が主要工業国に復帰するのはまだまだ先のことだと考えられていました。
しかし潜在的には大きな関心事でした。
特に日本が世界の中で独自の役割を果たそうとするかもしれないからです。
そういうときは、「拒否権」が大事な外交手段となります、、、
第二次世界大戦が終り、ソ連が東欧を獲得しました。
一方、「大領域」はその他の世界のほぼ全域に及ぶことになりました、、、
脅威はドミノ理論(一国が共産化すると周辺諸国も連鎖的に共産化するという考え方)で拡大されました。
もし独自の発展が一カ所で確立されると、近隣のドミノも倒れるかも知れないというわけです。
チリのアジェンデ政権が社会民主主義を押し進めたとき、キッシンジャーは「病原体」が感染を広げかねないと警告しました。
それもラテンアメリカだけでなく、南ヨーロッパまで伝染するかも知れないというのです。
当時、南ヨーロッパは社会民主主義の一形態「ユーロコミュニズム」の脅威にさらされていたのです、、、
彼が心配したのは、”議会制度を通じて大きな社会変革が起せる”というモデルでした。
独立した発展は他の人々に刺激を与え、米国の経済的浸透や政治的支配の邪魔をするかもしれません。
それを心配したのです。
ドミノ理論は、ドミノ倒しが起こらないを笑われます。
しかし、この理論が破棄されることはありません、、、
冷戦も実際に起こったことを考えると再解釈が必要です。
冷戦とは超大国がそれぞれの所有地域に介入し、支配を確実にすることでした。
その言い訳として敵の脅威が使われたのです。
お互いの優位を保つため、何度も超大国間の衝突が起こりかけました。
衝突が起こっていれば、地球は人類が住める場所ではなくなっていたでしょう。
今でもその危険は残っています。
新しい世界秩序の中における日本の役割は、米国の政策立案者たちにとって重要な関心事でした。
米国の内部資料を読むと、1950年代からベトナムに介入した米国の動機は、正統的は「ドミノ理論」が大きな理由となっています。
これに従うなら、ベトナムで独自の発展が成功すると、近隣諸国も同じ道を歩むかもしれません。
その動きが資源豊かなインドネシアまで到達すると、独立した東南アジアに日本が受け入れられ、工業と技術の中心地になる可能性が出てきます。
そうなると、戦前の日本のファシストたちが確立しようと狙っていた秩序が実現することになります。
日本史の専門家ジョン・ダワーが述べたとおり、日本は「スーパードミノ」であり、倒れたら大変です。
米国が恐れたのは日本の共産主義化よりも、米国が支配する「大領域」の外側における独自の発展に、日本が組み込まれることでした、、、
米国の国力(パワー)は1945年に頂点を迎えていますが、長続きはしていません。
1949年になると米国の力は衰退をはじめています。
「中国を失った」と呼ばれる出来事が起こったためです。
「失った」というのは、それまで米国が所有していたということです。
中国を失ったため「大領域」は縮小されましたが、それだけでなく大きな国内問題も起こりました。
この「中国を失った」のは誰の責任かという問題が「マッカーシズム(赤狩り)」という抑圧を生んだのです。
この抑圧によって進歩的勢力は大きく衰退しました、、、
1970年代初めになると、世界経済は三極体制になります。
米国を中心とする北米、ドイツを中心とするヨーロッパ、日本を中心とする北東アジアです。
この頃の北東アジアはすでに世界一ダイナミックに成長する地域でした、、、
1990年代から、多国籍企業による国家の支配が強まっています。
多国籍企業は国家政策の後押しを得て、国際的な分業体制をどんどん構築しています、、、
この新興のグローバル化されたシステムの巨大な規模は、2013年に国連貿易開発会議の世界投資報告書によってあきらかにされています。
それによると世界貿易の80%は、多国籍企業群が支配する国際的な分業体制の内部で行なわれ、世界の雇用の20%を占めるそうです。
このグローバル化した経済の所有者について、政治経済学者のショーン・スターズが深く研究しています。
彼の結論には説得力があり、国の富をGDP(国内総生産)で測る従来の方法は、新自由主義(ネオリベラリズム)のグローバル時代においては、大きな誤解を生むと指摘しています。
複雑で統合されたサプライチェーン(供給販売網)や下請けなどがあり、世界の富や権力を語るには、
国の富よりも、企業の富を見るほうが現実的だというのです。
世界は国別の政治経済というモデルから大きく変わってきているのです。
スターズが企業による所有を調査したところ、製造、金融、サービス、小売りなどほぼ全分野において、世界経済を所有しているのは圧倒的に米国企業であることが判明しました。
米企業による所有率は全体の50%に迫っています。
これは米国のバワーが歴史的に強かった1945年の最大推計とほぼ同じです。
従来の測り方だと、米国の富は1945年から低下して、現在は世界の20%ほどでしょう。
しかし、米国企業のグローバル経済の所有率は爆発的に高まっています。
ネオリベラルによるグローバル化によって、ケナンの考え方は階級という面から修正が必要です。
地域による格差を認識したケナンは、その格差を保つべきだと主張しましたが、今では言い換える必要があります。
国家間ではなく、階級に格差が生じているからです。
大企業は国家に頼る一方で、支配もしています。
ただ、このような関係は新しいものではありません。
18世紀の英国を説明するのに、アダム・スミスは「人類の支配者たち」について述べています。
当時の支配者たちは、商人と製造業者でした。
彼らは国家の力に依存していましたが、同時に自らの力を使って、自分たちの利益を政治制度の中で守っていました。
彼らはその影響が他の人々にとっていかに「悲惨でも」気にしませんでした。
現在の支配者たちは巨大な複合企業群であり、金融操作に焦点を合わせていますが、基本的構造は変わっていません。
本書では、これまでの枠組みである国家権力の面からさまざまな検討をしていますが、これは正統的な方法であり役に立ちます。
しかし、ここで簡単に触れたように階級と国家の関係もさらに分析が必要です。