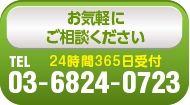99歳肺がん患者「間もなく死ぬのに死ぬことも選ばれへん」〝最期〟の覚悟と意思疎通 安楽死「さまよう」日本(2) – 産経ニュース
《私に死が迫っている場合や、意識のない状態が長く続いた場合は、死期を引き延ばすためだけの医療措置は希望しません》
尊厳死の法制化を目指す日本尊厳死協会が例示する事前指示書(リビングウイル)には、そんな文言が並ぶ。希望者は署名するが、撤回もできる。同会では現在、約7万6千人分を保管する。
東京都の堀江昌子(83)は、2002(平成14)年に事前指示書を作成した。終末期、緩和ケアは受けるが、延命治療は一切望まない。2人の息子にも折に触れて意志を伝えている。
尊厳死を望む気持ちは17年前、88歳の母を見送ってより強くなった。
「延命治療などで、絶対に生き永らえさせないで」。早くから事前指示書を用意していた母は、事あるごとに口にしていた。だが、いざそのときを迎えると、本人の最後の希望をかなえる「当たり前のこと」は、簡単ではなかった。
「お母さんを殺す気か」医師の言葉に失望
08(平成20)年、母が重度の脳出血で倒れ、救急病院に担ぎ込まれた。母の希望を伝えると、医師は言い放った。「お母さんを殺す気ですか」。捺印(なついん)のある延命治療中止の要望書も提出したが、認めてもらえない。失望感に言葉も出なかった。
やむを得ず、かかりつけ医を頼って転院。医師の同意を得て延命治療を中止した。静かに眠る枕元で、母が好きだった音楽を流した。翌日、母は旅立った。
「何十年と生きてきた自分の最期は、自分で決めたい」。堀江の強い思いだ。同時に「本人や家族、医師にとって望まない結果を招かないためにも、事前に意志表示して話し合うことが重要」と考えている。
厚生労働省が07(平成19)年に公表した延命治療の不開始・中止を事実上認める指針でも、患者本人や家族、医療従事者が十分に話し合う必要性が唱えられている。
だが、同省が22(令和4)年度に行った意識調査(有効回答3千人)で、終末期医療に関する希望について「考えたことがある」が5割を超えたのに対し、家族らと「話し合ったことがある」は3割にとどまった。死をテーマに臆さず話し合える家族は決して多くない。
国は、人生の最期に自分が望む医療やケアを受けられるよう家族や主治医らと共有する「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」を推奨しているが、「知っている」と回答したのはわずか5・9%だった。
患者より家族の思い優先
「日本の終末期医療の現場では、本人の意志より家族の思いが優先されるケースが多い」。大阪市の看護師、中末温美(51)は実感している。
99歳の肺がん患者の女性は、延命治療を望まないと書面に記していたが、家族は点滴を求め続けた。前の病院では、嫌がる女性の体を縛り付けて点滴していたという。「間もなく死ぬのに、死ぬことも選ばれへん」。中末につぶやいた。
家族と医師らが話し合い、家族は女性の希望に沿うことにいったんは同意した。しかしその4日後、女性の容体が変わると、家族は再び点滴を求めた。「患者さんの気持ちを思うとつらいが、家族から求められたら、医師は従わざるを得ない」
ほかに、家族に押し切られる形で胃瘻(いろう)を造設した80代男性がこぼした言葉も忘れられない。「生き地獄やな。なぜここまでして生かされるのか」
中末が現場で痛感したのは、家族同士のコミュニケーション、理解不足だ。経験を踏まえ、切実に感じる。「日頃からの当事者と家族の意思疎通、死に向き合う覚悟が必要なのではないでしょうか」