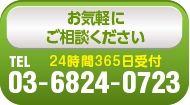9月末、大阪府保険医協会総会に出席させていただき深く感謝いたします。
講演で私は、評論家で医師の加藤周一さん(1919ー2008)の「公共」の思想にふれた。
加藤さんは、世のなか全体を俯瞰する視点と、ミクロの個々人の自発性を見つめる目とをもって、その両方を往復する運動から公共が立ち現れると説いた。
つまり、公共とは、全体主義ではなく、個々の特性や自発性を尊び、全体と個をつなぎ直す持続的な対話と営みによって生まれる領域といえるだろう。
このような公共の典型が「国民皆保険制度」だ。
都市の開業医の方々は、日々、皆保険の意義を実感しておられると思うが、そのルーツが農民たちの皆保険への切なる願いにあったことにも心に留めていただきたい。
1919(大正8)年、島根県鹿足郡青原村(現・津和野町青原)で産業組合が中心となって、農民有志が資金を出しあい、医師を招き診療所を設けた。
「農民が医師を雇ったこと」が「農民皆保険」への第一歩だったのである。
この「医療利用組合」方式の医療機関設立運動は全国の農村そして都市へと波及していく。
教育者の新渡戸稲造たちは、1932(昭和7)年に「東京医療利用組合」を創設、翌33年には「中野組合病院(現・新渡戸記念中野総合病院)」を立ち上げた。
さらに38年、「国民健康保険法」が公布され、当時の国民の6割を占める農山漁民を対象とした巨大な医療保険が滑りだしたのだ。
しかし、、、敗戦で日本の医療は崩壊。
進駐したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって、「上からの医療の民主化」が進められた。
当時、佐久地方では、若月俊一医師(佐久病院名誉総長)が出張診療や演劇による健康講話などの手法を駆使し、「現場からの医療の民主化」を村人にわかりやすく伝えた。
その際、最も活躍したのが、家父長制と寄生地主制に虐げられてきた農村女性たちだった。
農業協同組合の婦人部が中心となって、農村保健が日本の町村に浸透していったのである。
戦後80年の間、皆保険制度は全体と個の間を往復しながら、整えられてきた。
だが、いま、国民医療費の膨張ぶりが、制度の在り方に深い影を落としている。
じつは、国民医療費には、ひとつの盲点がある。
「予防は治療にまさる」というが、予防と治療それぞれの具体的費用の詳細を調べる研究が進んでいない。
この調査を、早稲田大学大学院の兪炳匡(ゆう・へいきょう)教授が進めつつある。
兪教授が、予防につながる行動変容のために提唱している即興の「健康教育劇」の取り組みが次第に浸透し、佐久では市民劇団の創設につながって、これまた皆保険の精神を下支えする自覚の広がりをみせつつある。
地理的・社会的なへき地で暮らす人びとの視点で、コミュニティの協同の力を生かすこと。
そして、適正技術と、失われつつある古来の知恵や技、諸学の力を結集することで、21世紀の「新しい農村医学」が確立されるのではないか、と期待いたしたい。
農村医学とは、「農」民牧民先住民の「村」落共同体に向けた「醫」(ケアと祈り)の「学」際的適用である。
色平 哲郎(いろひら てつろう)
JA長野厚生連・佐久総合病院地域医療部地域ケア科医長
大阪保険医雑誌2025年11月号掲載