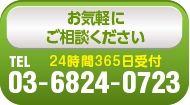発見まで4カ月 自宅で白骨化、引き取り手なく…孤立死2万人時代に問われる最期の迎え方(産経新聞) – Yahoo!ニュース
1人暮らしのまま自宅で亡くなり、発見まで時間がかかる「孤立死」が広がっている。
内閣府によると、昨年の推計値は2万人超。引き取り手がなく自治体が火葬するなどした遺体は、令和5年度で約4万2千人と公表された。
未婚などの影響で単身高齢者の急増が見込まれる中、国は5月を孤独・孤立対策強化月間と位置付けており、孤独・孤立の予防などに重点を置いた態勢整備を急ぐ。
■「洗濯物」で違和感
昨年6月、大阪市阿倍野区のマンション一室で白骨化した遺体が見つかった。
推定年齢は60~70代で、死後4カ月以上が経過。洗濯物が長期間干されたままの状態を不審に思った住民が管理人を通じて警察に通報した。
大阪府警は1カ月近く捜査したが、引き取り手は見つからなかった。
身元特定に至らない遺体は「行旅(こうりょ)死亡人」として扱われる。
「自宅で亡くなったはずなのに…」。火葬などを担当した阿倍野区役所の職員は、やるせなさを感じながら手続きを進めたという。
■2050年は4割が単身世帯
内閣府が今回初めて推計した6年の孤立死者数(自殺を含む)は、2万1856人。取りまとめを担当した有識者作業部会(座長=石田光規・早稲田大文学学術院教授)は死後8日以上経過して発見されたケースを孤立死と位置付けた。
一方、厚生労働省によると、引き取り手がなく自治体が5年度に火葬や埋葬をした遺体は4万1969人と推計され、5年の全死亡数の2・7%にあたる。
大阪市では引き取り手がない遺骨は1年間保管し、期間経過後は毎年9月に無縁仏として市設霊園に合祀(ごうし)する。 孤立死などによって引き取り手が見つからない遺体は今後増えることが懸念される。
国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2050年には全5261万世帯の44・3%に当たる2330万世帯が単身世帯となる。65歳以上で1人暮らしの男性のうち未婚者の割合は約6割と見込まれる。
■社会全体の課題
こうした状況で政府も孤独・孤立対策に力を入れる。昨年6月に策定した重点計画で、孤独・孤立は「人生のあらゆる段階で何人にも生じ得る」として「社会全体の課題」と位置付けた。
対策では、孤独・孤立の実態を把握しながら、SOSを求めやすい環境を整備するとともに、声を上げられない当事者に支援を届けるための態勢構築が求められる。
政府は令和6年度に対策を講じる都道府県向けの交付金を創設。7年度は市区町村にまで対象を拡充し、今年3月末時点で297団体に計約17億円の交付を決定した。
具体的には、人と人のつながりを広げるために官民が連携する基盤(プラットフォーム)の構築を進める。
個別事業ではひきこもり・就労支援のほか、見守りや相談窓口に携わる人材の育成などが含まれる。ある自治体の担当者は「地域で安心して生活できる土台をつくる」と話した。
■ひとりでも「終活せず」8割
「おひとりさま」といわれる身寄りのない単身者の終活(ソロ終活)について、高齢者支援サービスなどを提供するITメディア「鎌倉新書」(東京)が調査したところ、自身の死後に不安を抱えながら準備ができていない状況が明らかになった。
同社は、60代以上の単身者のほか、夫婦のみの「おひとりさま予備軍」を対象に平成31年4月にインターネット調査を実施した。有効回答数は556件。
調査によると、ソロ終活に「興味はあるが準備していない」が53・5%に上り、理由は「何をすべきかわからない」「誰に何を頼むかを具体的に決められない」といった回答が多かった。実際に準備をしている人は19・6%だった。
一人で最期を迎えることに「不安がある」との回答は45・7%。
主な理由に「後のことを託す人がいない」「孤独死を避けたい」などが挙げられ、不安に感じること(複数回答)は、役所への届け出などの死後事務や遺品整理が多かった。
単身者が準備すべきこととして、同社オフライン事業推進室の檜垣圭祐室長は①入院時などに必要な「身元保証契約」②医療や介護の契約を代理で結んでもらう「任意後見契約」③死後事務の委任契約④遺産手続き-を挙げる。契約にも費用がかかるため「計画的に準備しながら、安心を得るために貯蓄しておくことが大事だ」と話した。
■必要な人に支援届く仕組みを
石田光規・早稲田大文学学術院教授(社会学)の話
日本の人口構造をみると、就職氷河期に社会人になった団塊ジュニア世代を含む現在の50代は、未婚率が高く、孤立死の割合が多い。50代は年代別人口のボリュームゾーンで、1人暮らしの高齢者が今後急増する状況に対応しなければならないのが日本社会の現実だ。
政府の孤独・孤立対策には、現に問題を抱えている人への支援と、孤独・孤立の予防という両方のアプローチがある。前者については、対策の内容や関係省庁の担当分野を整理し、医療や福祉にとどまらない分野横断的な対応が必要だろう。
問題は後者だ。社会とのつながりや居場所をつくるための対策は押し付けになってはいけない。とはいえ、孤独や孤立に陥る人は自分から居場所を求めたりしない。
現代社会は、一人でも生きていけるシステムが整っている。煩わしい人間関係を避けるようになると、人や社会とつながる意欲を失い、孤独・孤立の一歩手前までいってしまう。つながりが希薄な社会を生きているという自覚を持ちながら、本当に支援が必要な人に届ける仕組みをつくることが喫緊の課題だ。