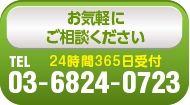自殺幇助が合法の国で安楽死を望む「デスツーリズム」 スイス民間団体に日本は98人登録 安楽死「さまよう」日本(4) – 産経ニュース
「デスツーリズム」と呼ばれる渡航がある。安楽死や自殺幇助(ほうじょ)が禁じられる国で重い病などに苦しむ患者らが、認められている国に渡り、致死薬の投与や処方を受ける。
スイスの民間団体「ディグニタス」では、1998~2023年に計3916人が自殺幇助を受けた。うち3675人(94%)は海外在住者で、日本の6人も含まれる。同団体は会員にスイスの医師を紹介、医師が致死薬の処方箋を出し、会員は団体の施設で自ら服用、摂取する。会員数は23年末時点で1万3775人。日本からは98人が登録している。
日本と同様に安楽死が認められていないフランスからも少なくない。同団体で23年までに自殺幇助を受けたフランス在住者は549人。また、ベルギーの担当部局の報告では、22~23年に同国で安楽死した外国人170人のうち、154人をフランス在住者が占めた。
「病状に好転する希望はなく、彼女は心から死を望んだ。母国ではかなわないから、やむなく渡ったんだ」。四肢まひに苦しみ、24年2月、ベルギーで安楽死したフランス人、リディ・イムホフ=当時(43)=に同行した元麻酔科医のドニ・ルソーは、そう振り返った。
尊厳死、仏では20年前に法制化
フランスで安楽死が禁じられてきたのは、カトリック信仰の宗教観に由来する。ただ、日本とは異なり、尊厳死は20年も前に法制化されている。
痛みなどを取り除く緩和ケアの実施を条件に、延命治療の中止を認める「レオネッティ法」が制定されたのは05年。16年には、終末期患者を対象に、より強い鎮静効果のある薬の使用を認める改正法が制定された。
同法制定のきっかけとなったのは、交通事故で四肢まひになった男性の訴えだった。03年、男性側が安楽死を認めるよう求める手紙を大統領に送ったことがメディアに取り上げられ、国民的議論に発展。改正法の前段でも、終末期医療に関する大規模な実態・意識調査や、半年にわたる全国での市民討論会が行われ、関心を高めた。
さらに、フランスでは23年以降、安楽死法制化への動きも顕在化した。しかし、24年の欧州議会選での与党連合敗北など政治的混乱を受け、法案審議は頓挫した。
ただ、法整備の必要性を唱える声は途絶えていない。独立機関「国家倫理諮問委員会」委員長の医師、ジャン=フランソワ・デルフレシは「時代や宗教観によって終末期への考え方は異なる。法整備で全ての患者に機会が平等に提供されることが重要だ」と語る。
「終末期の基本的人権を守る法の制定を」
尊厳死も法制化されていない日本では、厚生労働省が2018(平成30)年3月、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という概念をガイドラインに盛り込んだ。人生の最終段階の医療・ケアが自身の望むような形で行われるよう、家族や主治医らと事前に繰り返し話し合うことを推奨している。
延命治療を巡る本人と家族らの齟齬(そご)を防ぐことにつながる手立てだ。しかし、提示から7年たった今も、一般にはほとんど認知されていない。
「尊厳死をめぐり、フランスには20年来の議論の積み重ねがある。日本では国民的レベルの議論がほぼなかった」。フランスの制度にも詳しい衣笠病院(神奈川県横須賀市)の医師、武藤正樹(76)は「日本ではまだ尊厳死法制化のハードルは高い」と指摘する。
ただ、武藤は日本でも、終末期について国民が正面から向き合う機会を積極的に設けていく必要があると考えている。
「苦痛から逃れる権利、過剰な医療を受けない権利。自らの意志を伝える、いわば終末期の基本的人権を守る法の制定は、目指すべきではないか」