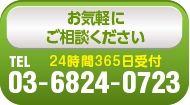子どもの集団で起こる「いじめ」の構造を知っておくことは、いまや大人の責務だろう。
子どもの自殺数が2023年、24年と2年連続で500人超の「異常事態」が続いている。
いじめが絡んでいる。
大人が、早く気づいて、手を打てば救えた命があったはずだ。
子どもは「純粋で無垢」だとは限らない。
家や社会で弱い立場に置かれた子どもは権力に飢える。
強権的支配を受ける子ほど権力欲は強まり、大人の態度からいじめの方法を学ぶといわれる。
では、治外法権のような学校で、いじめはどう高じていくのか。
この罠のような構造を解き明かしたエッセイがある。
精神科医で、自身が戦争中いじめられた経験を持つ中井久夫医師の「いじめの政治学」(中井久夫集6)だ。
中井先生は、いじめのプロセスを「孤立化」「無力化」「透明化」の三段階に分けて解説している。
論旨をざっとまとめてみよう。
いじめっ子は、まず、ささいな身体的な特徴や癖などに目をつけ、標的にした子どもを「孤立化」させる。
「こいつは、こんなにも鈍い、醜い」といった「PR作戦」を展開、誰がマークされたかを周りに知らせる。
すると狙われなかった子たちはホッとし、標的から距離を置く。
PR作戦は標的の子にも影響を及ぼし、自分は魅力のない生きる値打ちのない独りぼっちの存在だと思わせる。
そして、加害者は、被害者に「反撃は一切無効だ」と懲罰的で過剰な暴力を振るい、誰も味方にはならないことをくり返し味わわせ、「無力化」していくのだ。
「大人に告げることは卑怯」と心理的な枷まではめる。
そうした状態で、被害者は、周りの大人に「いじめに気づいて。覚って」とサインを出すが、大人は気がつかない。
やがて第二次大戦中、ドイツ人には強制収容所があっても「見えなかった」ように、被害者の存在は透明化されていく。
加害者との一対一の関係に縛られた被害者は、一見、加害者と仲良さそうに遊んだりもする。
いじめが、ふざけているようにしか見えず、大人たちは「子どもの世界に口出しはよくない」「自分もいじめられて大きくなった」と弁明する。
かくして被害者は、奴隷化され、金銭をたかられて、万引きし、犯罪まで背負わされるのだ。
こうならならないよう、大人はどうすればいいか。中井ドクターは、こう記す。
〈冗談やからかいやふざけやたわむれが、いじめでないかどうかを見分けるもっとも簡単な基準は、そこに相互性があるかどうかである〉〈まず安全の確保であり、孤立感の解消であり、二度と孤立させないという大人の責任ある保障の言葉であり、その実行である〉〈被害者がどんな人間であろうと、大人は、いじめは基本的に悪であり、立派な犯罪であり、道徳的には被害者の立場に立つことを明言する必要がある〉
学校現場に限らずどの職場も、長時間労働のうえ細部にわたる外部評価が伴う厳しい現状だ。
とはいえ、故中井医師の洞察を胸に刻んでほしいと、切に願う。
色平 哲郎(いろひら てつろう)
大阪保険医雑誌2025年3月号掲載