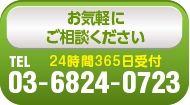ふり返れば、多くの患者さんを看取ってきた。
山村の診療所長だったころは、在宅で家族に囲まれて大往生を遂げたご老人の診断書を書いた。
病院では、ときに病理解剖に立ち会い、終わったらご遺体を迎えの車に乗せ、頭を垂れてお見送りをしてきた。
われわれ医師は、そこで「終わった」と思いがちだ。
が、その後、人間にとって大切な儀礼が待っている。
葬儀である。
故人の死を悼み、遺族を慰める「弔い」は、人が必ず直面する死の悲しみを受け入れ、遺された者が心中を整理、故人との別れを実感する大切なプロセスだ。
浄土教系の仏教は死を極楽往生の機会ととらえ、キリスト教は死で魂が神のもとに召されると説き、イスラームは死を超越神アッラーが定める一時的なお別れととらえ、魂がふたたび肉体と結びついて復活する、と信じている。
遺体を火葬にするか土葬にするかは、それぞれの宗教や、社会的な要因に基づいて決まる。
イスラームや東方教会は土葬、西方キリスト教は土葬が主流で火葬も受け入れる。
日本では、年間150万体を超えるご遺体の99・97%が火葬にされている(2021年度・厚生労働省データ)。
こうした葬儀が、最近、様変わりをしている。
「【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年)」(鎌倉新書)によれば、葬儀経験者の有効回答2000件のうち、じつに「家族葬」が50%を占める。
家族葬とは、通夜・葬儀がある形式で、参列者が親族や近親者のみとされる。
次に多いのが「一般葬」で30・1%。
これは家族、親族だけでなく知人、地域や職場の人も通夜・葬儀に参列する形だ。
かつて、バブル経済の隆盛期には、庶民の葬儀でも200~300人も会葬者が集まる一般葬が珍しくなかったが、バブル崩壊後、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災を経て葬儀の「薄葬化」が進んだ。
経済的理由と、故人をよく知る家族や友人で心をこめて見送りたいという意識が強まったようだ。
そして、コロナ禍で「3密の回避」が叫ばれ、家族葬が主流になった。
家族葬よりも小規模化、個人化した葬儀も増えている。
前述の調査でも、通夜がなく告別式だけの「1日葬」が10・2%。
宗教的な儀礼がなく火葬のみでお別れの「直葬・火葬式」が9・6%とつづく。
直葬の場合、死後24時間は法律で火葬が禁じられているので、遺体をいったん安置する。
その後、火葬場に運んで荼毘にふす。
火葬後、遺骨を骨壺に納める「骨上げ」は、東日本では遺骨をすべて拾う「全収骨」、西日本では一部の遺骨のみを拾う「部分収骨」が一般的だ。
骨壺を自宅に保管する「手元供養」も増えているらしい。
弔いの個人化、小規模化は、超高齢社会を背景に今後も進みそうだ。
どのような形式であれ、世代をつなぐ葬儀が大切な儀礼であることは間違いない。
「骨を砕いて粉と為し、之を山中に散らすべし」と遺言した淳和天皇や「それがし閉眼せば、加茂川に入れてうほ(魚)にあたうべし」と言い残した親鸞の最期を想い起こした。
色平 哲郎(いろひら てつろう)
大阪保険医雑誌2024年12月号掲載