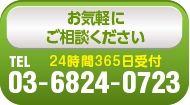日本では他者への信頼度がとても低いことがわかります。
反対に、ベーシックサービスのように、《だれもが受益者》という戦略を意図的にとっている北欧諸国では、他者への信頼度がきわめて高いことが知られています。
北欧にはいい人が多いんでしょうか?ちがいます。
人を信頼したほうが得をする社会を彼らは作りだしたのです。
サービスの「配りかた」 こそがカギなのです、、、
生活扶助の充実、失業給付の拡大、住宅手当の創設といった「命の保障」は不可欠なものです。
ただし、命の保障を「最低限」という言葉だけで片づけてはいけません、、、
命の保障は、たんなる最低限の保障ではなく、《品位ある最低保障》(decent minimum)でなければならないのです、、、
《弱者を助ける》から《弱者を生まない》への転換をめざす。
運の良し悪しで一生が左右される人たちの命を保障する。
そんな《中低所得層のあたらしい同盟》こそが、僕の思いえがく理想社会の大切な柱なのです、、、
1976年にILOが開催した会議で「ベーシックニーズ」という考えが提案されました、、、
(1)食糧、家や施設、衣服などの個人的に消費される基本物質
(2)共同体で提供されるべき安全な飲料水、衛生環境、公共交通、健康、教育などのサービス
そして暗示的にではありますが、
(3)これらに影響を与える意思決定への人びとの参加、、、
ベーシックサービスと品位ある最低保障を車の両輪とした社会を、僕は《ライフセキュリティの社会》と呼びます。
命と生活、すなわち「ふたつの生(=life)」を保障しあう社会という意味です。
ライフセキュリティの社会は、お金とはちがう「ゆたかさ」をもたらしてくれます、、、
ベーシックサービスの無償化が多様性を支えるだけでなく、《ライフセキュリティの社会》を実現していくプロセスじたいが「共にある」という感覚をはぐくむ条件ともなっている点です。
哲学者ジョン・デューイが指摘するように、社会の基盤にある「共通理解」はモノのように手わたすことができません。
共通の目的をもち、関心をもち、それとのかかわりのなかで、自分たちの行動を決めていく、これらのプロセスをつうじて共通理解がはぐくまれ、共にあるという感覚がつちかわれていきます。
もちろん、人びとはみなが連帯し、手と手と取りあって、和気あいあいと生きていけるわけではありません。
議論をすれば必ず意見は食いちがい、対立が生まれます、、、
多様性を大事にする社会、それは人間の自由を尊重する社会です。
ただし、そんな魅力的な社会は、権利としての尊さを説いて満足するだけでも、すたれゆく経済にまかせっぱなしにするだけでも、絶対に作れっこないのです。
命や暮らしの心配がない社会が生まれたら、だれもまじめに働かなくなるんじゃないか、と思っている人はいませんか?
やさしくしすぎると人間はダメになる。
この点は終章で掘りさげますが、ありがちなこの発想はデータ的に根拠にとぼしい話です。
先進国のなかでも租税負担が高く、生活保障が充実している北欧と比べてみましょう、、、
国際競争力や経済成長率だけでなく、さまざまな指標をもとに作られた国連の「世界幸福度ランキング(2023年)」を見るとちがいは顕著です。
フィンランド1位、デンマーク2位、スウェーデン6位、ノルウェー7位にたいして、日本はなんと47位という状況です、、、
べつに北欧をめざそう、と言いたいわけではありません。
1990年代以降、私たちは「グローバルスタンダード」という名の「アメリカンスタンダード」を追いかけてきました。
ですが、私たちがアメリカになれなかったのと同じように、いくら北欧のマネをしても、同じ国になれるわけではありません、、、
これらのデータを見るかぎり、不安におびえる社会よりも、命や暮らしの支えをしっかりと作り、これを跳躍板として未知の領域にチャレンジできる国のほうが、経済的にも、社会的にも、ポジティヴな結果を生みだしているのではないか、ということです。
みなさんは、働ける人、働けない人、すべての人たちが将来への不安から解放される自由な社会をめざしたいと思いませんか?
井手英策「ベーシックサービス」99p、103p、105p、117p、122p、124p
欧州の常識
「貧困と不公平などの削減にもっとも成功した国ぐには、富裕層に課税し、貧困層に与えることでそれをやりとげたのではない」ノースウェスタン大学 モニカ・プラサド
「逆進的な税しか採用していない国でもその収入で社会保障を積極的におこなっているのであれば、その国全体としては逆進的ではない」フランス主税局官僚 フィリップ・ルビロア 1972年
井手英策「ベーシックサービス」89ページ(一字修正)と90ページ
カネと運しだいの自己責任社会を変える本
教育費・医療費・介護費・障がい者福祉がタダになり、将来の不安におびえて今の望みをあきらめなくてもいい、衝撃の方法があった!
「そもそもコメは足りてないんですよ。生産量が足りてない。『もうコメは作らないでいい、田んぼは潰しましょう』と、米農家は赤字で苦しんでても放置されてきたわけで、生産が減りすぎていたところに猛暑があった。
政府は作況指数は100を超えて取れているといいますが、現場はそんなに取れてないとみんな言っています。かつ品質が落ちているから、精米にしたときに、いわゆる普通の主食米として売れる量が減っているわけです。」

最後に主催者として付け加えるのであれば、「普遍性」と言った場合に、欧米キリスト教世界中心のあるいは日本も含む経済大国中心の無反省で傲慢な「普遍主義」ではなく、またそれを脱却するとしても「すべては相対的にすぎない」と批判の基準さえも放棄するのではなく、被抑圧者あるいは第三世界に共有される「新しい普遍性」をいかにして構築できるのかというエドワード・サイードや徐(京植)さんの問い掛けは重要だが、しかしそれを、日本社会のマイノリティである徐さんやユダヤ人のロイさんに提起してもらってそのおこぼれに預かるのではなく、例えば日本社会のマジョリティである日本人としての私がいかにして自己批判をしながら「新しい普遍性」を目指すのか、ということが問われている。 (文責;早尾貴紀)

「貯蓄ゼロでも不安ゼロ」の社会!
(書評より)MMT亡国論 働けなくてお金がない人の社会保障をどうするか
改めて再読してみるとスウェーデンの経済学者ミュルダールの「消費の社会化」が思い浮かびました。
生活する上で必要な教育・医療・介護などのサービスやモノの消費(特に子供に関すること)を国がサポート(社会化)するというミュルダールの考えはベーシックサービスに通ずるものがある気がします。
MMT(現代貨幣論)についてかなり批判的なことを書かれています。
しかしすでに一部の信者以外にはオワコンになっているMMTへの批判は死体蹴りに等しいでしょう。
MMTが有効なのは強い貨幣という条件がないとだめで、かつて日本のMMT信者はすでに通貨安になりつつある「円」を過信しすぎていた。
もしくはアメリカの学者が強いドルという前提を当たり前としていたのに日本のおっちょこちょいさんが持ち込んだ際に抜け落ちてしまった。
増税がわりの国債大量発行の結果の円安はボディーブローのように少子化高齢者ばかりの衰退日本に効いています。
MMT信者の言う「政府の借金は国民の資産」の国民は上級国民を指しそれ以外の非国民(下級国民ともいう)が国の利息付借金を税金で返済しているのです。
さらに国債を経済成長の名のもと野放図に発行すれば、今以上に非国民の税金の支払う額が増えることになるでしょう。
もちろんいくら国に借金があろうが財政破綻はしません。
支出を減らせばいいのですから。
もう施設介護・在宅介護は下級国民にとって身分不相応なぜいたくです。
上級国民は有料老人ホームに行けます。
国の借金の返済で社会保障が減り「施設に入れない下級国民は認知症になっても自宅で糞尿まみれになりなさい」というのが今、国が行っていることです。
社会保障が信用できないが増税は嫌だ、投資をして老後資金を賄う。
そのような低負担低福祉の社会では稼げなくなってカネも尽きたら質の低い福祉しか受けられないのです。
それは間違っているというのが井手先生の主張で全世代が負担を増やして信頼できる社会保障を築こうという考えなのです。
井手英策「ベーシックサービス」「貯蓄ゼロでも不安ゼロ」の社会
お金による救済は人間の心に屈辱を刻み込みます、、、ですから、お金をサービスに置きかえることで、だれかを救済する社会ではなく、みんなが権利として、他者と区別されずに堂々とサービスを使える社会に変えていくべきだと考えたのです。(72ページ)
他者の存在、他者の価値を肯定する社会は、他者が私という存在、私の価値をみとめる社会でもあります。「共にある」という感覚をもった社会は、他者の価値を大事にすることは自分の価値を大事にしてもらうことに等しいということ、他者の自由が自分の自由と地続きであることを私たちに教えてくれます。(123ページ)
もし、税を前提にしないなら、こんな話しあいは、一切いらなくなります。好きなものを好きなだけ、しかも税金をはらわずに、手に入れることができるのですから。その意味でMMT(現代貨幣理論)を利用した政治主張は、政治の、民主主義の自殺行為なのです。(160ページ)
新書「ベーシックサービス」「貯蓄ゼロでも不安ゼロ」の社会