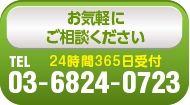働いている外国人の姿は、私たちの日々の暮らしのなかに溶け込んでいる。
介護はもとより、建物の解体や建設、コンビニや飲食店での接客などに外国人は欠かせない存在だ。
が、しかし、それに見合う「生存権」が保障されているのかと問うと、日本の行政の現状は、矛盾だらけで、とても保障されているとは言えない。
その事例をご紹介しよう。
ガーナ共和国の国籍を持つ男性、シアウ・ジョンソン・クワクさんが来日したのは2015年だった。
事業者に雇用され、納税もしながら働いていたが、18年に腎硬化症を発症。
働けなくなり、勤務先から解雇される。
その後は、週3回の人工透析で生命をつないでいる。
現在は支援団体の援助で国民健康保険に加入し、特定疾病療養の利用などで自己負担なしで医療を受けられている。
だが、在留資格が「特定活動(医療を受ける)」に限定されているために働いて収入を得ることが認められず、まったく収入がない状態だ。
ジョンソンさんは、千葉市に生活保護の申請をしたが、「外国人には生活保護を利用する権利はない」
と申請を却下された。
現在の取り扱いでは、永住者、定住外国人のみが、生活保護の対象とされている。
そこでジョンソンさんは、千葉市の処分の取消しなどを求めて千葉地裁に提訴した。
焦点は、生存権にかかわる憲法第25条の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた「国民」に外国人は含まれるかどうか、いわゆる「国籍条項」である。
ジョンソンさんは、国民に在日外国人も含まれると主張した。
その根拠の一つは、1954年5月8日の「社発第382号」厚生省社会局長通知だ。
これに「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと」と記されている。
しかし、2024年1月16日、千葉地裁はジョンソンさんの請求を却下、棄却した。
ジョンソンさんは、東京高裁に控訴したが、24年8月6日に棄却された。
国は、1954年の厚生省社会局長通知だけでなく、1981年に衆議院法務委員会で政府委員が
「実質的に内外人同じ取り扱いで生活保護を実施している」とも答えている。
一方で、1990年10月、厚生省の保護課担当係長が、口頭で永住者や認定難民だけが生活保護の給付対象と指示したため、在日外国人の除外がまかり通ってもいる。
90年代初頭、私は小諸のタイ人やフィリピン人の支援に奔走していたが、彼ら、彼女らの生活が困難な根底には、この係長の口頭指示があったのだ。
当時の私は、明治32年の勅令第277号「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に頼るしかなかった。
生活保護制度と出入国管理令との緊張関係はずっと続いている。
現在、ジョンソンさんは、最高裁に上告中だ。
外国からの働き手の皆さんが安心して働ける環境、病気や障害にも不安のない社会制度を構築することこそ、将来の国内就業人口を確保するために必要なことではないか?最高裁の判断が注目される。
色平 哲郎(いろひら てつろう)
JA長野厚生連・佐久総合病院地域医療部地域ケア科医長
大阪保険医雑誌2025年2月号掲載