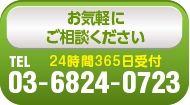信州から憂うパレスチナ3 「真の和平のためには」歴史授業の集大成
本質としての差別に気付く 信州イスラーム世界勉強会10年(3)
信濃毎日新聞2024年12月4日
「ガザ戦争を含むパレスチナ問題が『真の和平』に至るためには、どのような課題が解決される必要があると考えますか。自分はどのようなことができると考えますか」
11月11日、伊那弥生ヶ丘高(伊那市)3年の世界史探究の授業。
教諭の小川幸司さん(58)は、24人の生徒たちに質問をぶつけた。
2022年から始まった、日本史と世界史の近現代史を統合し考えることを重視する高校新科目
「歴史総合」。
その集大成としてパレスチナ問題を扱った。
「ちょっと復習しようか」。
小川さんは、第1次世界大戦後、米大統領ウィルソンやロシア革命を主導したレーニンが掲げた
民族自決の理念を振り返る。
「本来は個人にある自己決定権を民族単位で認めるというものだったね」。
民族自決は、植民地からの独立を果たす意味では正義に働くが、パレスチナのようにさまざまな民族が存在する地域では、民族対立の原因となることを改めて説明した。
1993年のオスロ合意は、イスラエルとパレスチナの2国家共存の和平実現につながると期待されたが、その一方で、オスロ合意を機に、パレスチナ人の移動はますます制限されて経済的に困窮するなど、現在のガザ戦争の火種となったことも指摘した。
小川さんは茅野市出身で、諏訪清陵高校を経て東京大でドイツ史を専攻。
高校の社会科教諭になり、松本深志や松川などで教えたほか、県教委で主任指導主事も担った。
中央教育審議会ワーキンググループの専門委員などを務め、歴史総合などの学習指導要領・解説作成
にも関わった。
同24日、小川さんの姿は長野市の信州大教育学部にあった。
同学部で開かれた日本中東学会。
テーマは「学校教育と中東・イスラームのいま」で、小川さんも県内外の研究者、教員ら70人の前で、自身の授業について報告した。
昨年春に高校の校長から一線の教員に戻り、イスラム社会に対する偏見とその偏見を押し付ける「オリエンタリズム」から脱却しようと現場で実践し続ける小川さんは、講演者にうってつけだった。
「どんな強大な国があったか」
「どのように国が統一されたか」
「どんな戦争があり勝敗はどうだったか」
を語ることが中心となっている歴史の授業に疑問を抱いてきたことを指摘。
パレスチナ問題を扱うことで、大国、強い男性指導者、統一政策を中心とした歴史の授業の刷新を狙っていることを話した。
「高校の歴史は、絶対的に正しい歴史の習得、暗記ではなく、膨大な史料を検討し、独善的にならないように自分なりの歴史叙述を練り上げることだ」。
講演の中盤にはこう強調し、大きな歴史だけでなく、現場で声を上げる民衆個人の声を扱う必要性にも言及した。
学会広報を担当した信大教育学部助教の野口舞子さん(40)=イスラム史=は、将来社会科の教員となる学生に向けて講義をしている。
「小川さんは、生徒と一緒に史料を批判的に読むことで、先入観や教科書の枠にとらわれず、自律的に歴史と向き合うことを教えている」と、その教育の姿勢を高く評価する。
11日の授業は50分の時間内では議論が深まらなかったものの、冒頭の質問への回答が後日、生徒たちから提出された。
「誰かを下に見るところから対立が生まれる」
「歴史に対して受動的になるのではなく、潜在的な人種差別意識を取り除いて見つめることが必要」
「自分の知識や意見が事実と異なっていないか、常に疑問を持ち、自分で答えを追求していくことが大切だ」
現在のイスラエルは、パレスチナ人の人権を侵害している。
ただ、パレスチナ問題の元をたどれば、欧州が長い間ユダヤ人への差別を放置してきたことがある。
それは、貧困や部落差別を放置し、満州移民を支持した日本の歴史にも重なる。
「生徒は、本質的なところに気付いている」
少子高齢化で日本では今後外国人労働者が増えるとされるが、一方で在日外国人へのヘイトも目立ってきた。
パレスチナの問題は自分たちの問題になりつつある。
「就職や進学など生徒たちの進路は違う。それぞれの現場や暮らしの中で今日の授業を反すうしてくれれば」。
パレスチナのために自分ができること。
小川さんにとっては、歴史の授業を教室で続けることだ。
「オスロ合意」
パレスチナの暫定自治を認めたイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)との「パレスチナ暫定自治宣言」。1993年に双方が調印した。
イスラエル軍は占領地から撤退し、5年間の暫定自治期間にエルサレムの帰属や境界画定、難民帰還など最終地位交渉を行うという内容だった。
94年、当時のアラファト・PLO議長、ラビン・イスラエル首相、ペレス同外相はノーベル平和賞を受賞。
仲介する米国はパレスチナ国家樹立を認める「2国家共存」に基づく和平案を提示してきたが、2014年以降、交渉は中断している。
イスラムの特殊性 強調する危うさ
信州大教育学部 (長野市) で11月24日に開いた日本中東学会の公開講演会では、地理教育が専門の荒井正剛・東京学芸大特任教授も講演した。
同大付属中学校に31年勤務し、地理の教科書執筆にも参加する荒井教授は、イスラムの特殊性のみを強調すると、むしろ否定的イメージを抱かせてしまう危険性を指摘した。
荒井特任教授は、同大付属中生徒160人と同地区の公立中生徒171人を対象とした、イスラムのイメージに関するアンケート結果を示した。
付属中の生徒はイスラム教の創始者や聖典、聖地などの知識はある一方、「理解しにくい」「遅れている」といったイメージをより強く持っていた。
「日本と比べて、1日5回の礼拝やラマダン (断食月) などを合理的でないと反応してしまうようだ」
とした。
実際のラマダンは日没後に食事を取ることができる。
「日本の年末年始のようなもの。近づくとわくわくする」
と話すイスラム教徒もいる。
荒井特任教授は、日本の暮らしとの相違点と共通点の両方を提示し、生徒の固定観念や常識を揺さぶる工夫を授業に持ち込む必要性を強調した。