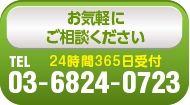森が必要とする時間の単位は、数十年から百年だ。
競争至上主義、成長至上主義で、世界同時性のスピードが求められる現代には、まったく不向きな代物である。
江戸時代の商人には、儲(もう)けたお金を運用するいい方途がなかったので、子孫のためには山林に投資したという。
江戸中期以降は、安易な新田開発が幕府から規制されていて「美田」はなかったのだ。
江戸期の前半は、全国的に各地で新田開発が取り組まれた。
人口も増加した。
室町期まで、人の手が入らずにきた「原野」が開発された時期である。
開発が進み次第にわかったことは、今まで原野だと思っていた里山などの共有地が実は、治山・治水の観点から見ると、重要な場所になっていた、という発見だ。
開発のしっぺ返しは、自然災害の形で現れた。
11年前、東信地方にはじめてやってきた私は、時を超えて人々の「記憶」が受け継がれていることにびっくりした。
8月1日の「お墓参り」がそれだ。
お盆よりさらに盛大な法事が行われるこの地方特有の鎮魂の行事は、260年前の大災害を今に伝えるものだ。
寛保(かんぽう)二年、前年寒中より雨数々降り、この年の春に至りなお雨日多く、夏に至りまた降雨うち続き、七月中ほとんど雨を見ざるの日なし。
就中(なかんずく)七月二十七日の夕刻よりふり出し……
終夜の強雨、八月朔日(ついたち)に至りなお雨はげしく、千曲川満水にて氾濫し、田中宿をつきてこれを流す……(「小県郡史」より)
小県郡の現・東部町、北国(ほっこく)街道・田中宿が、洪水の被害を受けたことが読み取れる。
私の近在では、現・八千穂村の甲州往還・上畑(かみはた)宿で、暗夜に堤防が決壊。
248人が溺(おぼ)れ死に、家屋140戸が流され残ったのは27戸だった。
現・小海町の本間村でも流死者こそ2名だったが、39戸が流された、と伝わる。
現在の暦(新暦)では8月末にあたるのだろう。
「二百十日」の雨台風だ。
古記録によれば、この台風は大阪湾に上陸し、京都で三条大橋を流し、信州各地を集中豪雨で襲った後、関東に抜け利根川を氾濫させた。
江戸でも、流死者や飢渇者が続出したという。
この大水害は、実は、治山・治水に配慮しないそれ以前の「開発」の強行によって傷を広げたものだった。
信州の被災地ではその後、人々はすこぶる困窮しながらも造林に手をつけ、山の保水力増強に努めることをもって、「鎮魂」としたと今に伝わる。
この時の造林の”精華”は、60年前、戦時中の木材供出によって、戦後は東京復興のために伐採された。
その跡には、戦後の「拡大造林」政策によるカラマツ植林がなされた。
芽吹き時のカラマツは、新緑がみごとな美しさだ。
しかしカラマツ林は保水力に乏しく、治山・治水にはほど遠い。
さらに十分な間伐、手入れをせずにこの数十年が経過し、森作りとしては言語道断の状況に陥っている。
「7世代後のことを考えて今を行動せよ」
との教えが、北米の先住民族にはあると聞く。
7世代とは、つまり200年のことである。
現代の我々は、200年後の子孫に何を残してやれるのだろうか。
朝日新聞長野県版 南相木村診療所長 色平哲郎 2001年4月26日