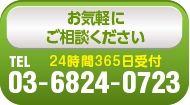閑吟集(かんぎんしゅう)は日本の小歌の歌謡集で、永正15年(1518年)に成立してます。
織田信長が生まれたのは、天文3年(1534年)5月12日ですから、閑吟集は、そのちょっと前の室町時代の戦乱期にの世相を反映している小歌集といえます。
現在、最も有名な歌としては、「一期は夢よ、ただ狂え」という実に短いのがありますが、これは49番~55番を通した中での、最後の歌となっておりますから、49番~55番を一つの歌とみなして、ここでは歌ってみました。
戦乱の世を生きていた庶民の心意気が如実に反映された歌といえましょう。
「人生なんて夢のように、はかないものさ」という人生観は古来よりある普遍的なものですが、「それゆえ、狂って生きようじゃないか」と、逆説的に人生を肯定的に生きる姿勢に室町人のしたたかさが感じられます。
室町時代は、日本史上の中でも、大飢饉が襲った時代であり、今日、今まで生きていた人が明日にはひょっこりと死んでしまった時代ですから、「一期は夢であり、それゆえ、今このひとときこそを、狂って生きようじゃうないか」と、逆に人々は、人生の一瞬一瞬に燃え尽きようとしていたのかも知れません。
蛇足ながら、「狂って生きる」とは、昨今のサイコパス的人間のように本当に狂って生きるのではなく、人生の本質をしっかりと見つめたうえで、生きるとは何か、その美を体現すべく、歌ったり、踊ったりして人生を肯定して楽しく生きようということです。
🎶♫•♬.♫•♫♫閑吟集「一期は夢よ、ただ狂え」🎶♫•♬.♫•♫♫
詩 閑吟集より 曲・歌 清水日風水
世間は、ちろりに過ぐる ちろり、ちろり(49番)
何ともなやなう、何ともなやなう うき世は風波の一葉よ(50番)
何ともなやなう、何ともなやなう 人生七十古来稀なり(51番)
ただ何ごともかごとも 夢まぼろしや水の泡 笹の葉に置く露の間に 味気なの世や(52番)
夢まぼろしや、南無三宝(53番) くすむ人は見られぬ 夢の夢の、夢の世を、うつつ顏して(54番)
何せうぞ、くすんで 一期は夢よ、ただ狂え(55番)