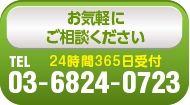今から500年前の1525年、暴力の吹き荒れる宗教改革のさなかに「再洗礼派(アナバプテスト)」と呼ばれるキリスト教の一派が生まれました。
彼らは幼児洗礼を否定し、兵役を含むあらゆる暴力を拒んだため、異端視され、迫害されました。
しかし「非暴力主義」をつらぬいた彼らの長年の信仰はやがて良心的兵役拒否の制度化につながり、現在では修復的正義(司法)、パレスチナ人とイスラエル人の和解の活動などにも影響を及ぼしています。
非暴力主義のあり方を改めて考えるために、踊共二著『非暴力主義の誕生──武器を捨てた宗教改革』(岩波新書、2025年)より、「愛敵と赦しの精神」にかんする箇所を一部抜粋して掲載します、、、
1614年、ランディスは刑場での斬首を前にパウル・フォルマーという刑吏から「これからわたしがしなければならないことを赦してほしい」と頼まれたとき、「もうとっくに赦しているさ。神もあなたを赦しているよ」と明るく答えたという。それを聞いた刑吏はランディスを縛っていたロープを緩め、両手を天に挙げて祈ったとされる。
『殉教者の鏡』によれば、刑吏の意図はランディスに逃走の機会を与えることであったが、彼は逃げることなく静かに処刑を待ったという。そして刑吏は命令(判決)どおりにランディスの首を刎ね、涙を流しながら「この人の血の責任はわたしにないことを神はご存じだ」とつぶやいたとされる、、、
ランディスの赦しの信仰が迫害者を共鳴者に、敵を友に変えたことに相違はない。
20世紀の公民権運動の指導者キング牧師(1929-68年)は、白人(敵)からどんな仕打ちを受けても愛と赦しをもって応えることによって敵を友に変え、迫害される側と迫害する側の「二重の勝利」「二重の解放」が得られると教えたが、これと同じことが17世紀の迫害社会のなかで起きていたということができる。
この倫理ないし信仰の実践の拠りどころは同じ聖書の箇所(イエスの山上の説教)であった。
愛敵、赦し、受難の信仰と結びついたノンレジスタンスの教えは、1632年にオランダ再洗礼派によって「ドルトレヒト信仰告白」の第14条に明示された。
すでに述べたように、スイス系の再洗礼派もこれを受け入れてメノナイト化し、そこから分かれたアーミッシュもこの条文の精神を守りつづけて現代にいたるのである。やや長くなるが、条文の全体を訳出しておきたい。
復讐について、つまり剣で敵に立ち向かうことについて、わたしたちは次のように信じ、告白する。
すなわち主キリストは彼の弟子たちとすべての信徒たちに対し、いっさいの復讐、報復を禁じ、悪をもって悪に報いず、呪いをもって呪いに報いず、剣をさやに収めよと言われ、かつて預言者たちが告げたように、剣を打ちなおして鋤とするように命じておられると。
マタイによる福音書5章39・44節、ローマ人への手紙12章14節、ペテロの第1の手紙3章9節、イザヤ書2章4節、ミカ書4章3節、ゼカリヤ書9章8・9節。
それゆえわたしたちは、キリストの模範に倣い、だれにも痛みや損害や悲しみを与えてはならないと考える。
逆にすべての人の至福と救済を追い求め、もし必要であれば主のために、ある都市や国から別の場所に逃れ、財産を奪われても耐え忍ばなければならない。
わたしたちはだれをも傷つけてはならず、もし打たれたときには報復することなく別の頬も向けねばならないのである。マタイによる福音書5章39節。
そしてそれだけでなく、敵のために祈り、彼らが空腹であれば食べさせ、渇いていれば飲ませ、かくして善き行いによって真意を伝え、無理解を克服しなければならない。
ローマ人への手紙12章19・20節。
最後になるが、わたしたちは善を行って万人の良心に訴え、キリストの法に従ってわたしたちが自分にしてほしくないことを他人に対してしない姿勢を保たねばならない。コリント人への第2の手紙4章2節、マタイによる福音書7章12節。
「非暴力主義の誕生」書評 現代人へ問う無名の人々の行為
評者: 中澤達哉 / 朝日新聞 2025年04月26日
非暴力主義の誕生──武器を捨てた宗教改革 (岩波新書 新赤版 2049) 著者:踊 共二 岩波書店
おどり・ともじ 60年生まれ。武蔵大教授。専攻はスイス史、中近世ヨーロッパ史。著書に『改宗と亡命の社会史』など。
「非暴力」といえば、世界史を少しでもかじったことがある人なら、真っ先にガンジーを思い出すだろう。あるいは、公民権運動のキング牧師かもしれない。
前者は、イギリス帝国主義に対抗する際に、あえてインドの人びとの「非暴力・不服従」を唱えた。後者は、アメリカ社会の白人支配に対して、黒人の権利を守る観点から「非暴力」的抵抗を主張した。
だが、本書のまなざしはこうしたヒーローたちには向けられていない。非暴力に徹したほぼ無名に近い人びとにこそ目を向け、歴史の闇の中から拾い上げようとするのだ。
時は遡(さかのぼ)ること近世。舞台は宗教改革の嵐が吹き荒れる欧州。暴力に彩られた時代は20~21世紀だけではない。近世の宗教改革期にも殺戮(さつりく)行為は横行し、極めて多くの人命が失われた。
こんな時代に、いっさいの暴力を拒んだ「再洗礼派」と呼ばれるプロテスタントがいた。
17世紀後半の史料によれば、同派の信徒たちは、迫害に対していっさい反撃せず、逮捕され、拷問(ごうもん)され、斬首され、焼かれるがままだった。さらに、同派を迫害に追いやった為政者に対して「赦(ゆる)し」まで口にし、むしろ祈りを捧げたのだという。
再洗礼派の行動がどこか常軌を逸したものに見えてしまうのは、私だけではないだろう。同派の行為は聖書に忠実だったことの証しだが、それ以上に本書はこの非暴力主義が現代に与えた影響を重視する。
欧米の良心的兵役拒否制度は、同派の非暴力主義なくして誕生しなかった。戦後、日米交流を米国側から先導したのも、同派だった。
私たちは反戦を唱えるだけでなく、再洗礼派のように、あらゆる形式の戦争協力を本当に拒否できるだろうか。実際に暴力に瀕(ひん)した際、命を賭して非暴力を貫くことができるだろうか。こうした問いは、キリスト教徒か否かに関わらず、戦争や人道危機が頻発する今だからこそ、私たち現代人に重くのしかかるのだ。
◇
評者: 中澤達哉(なかざわたつや) 早稲田大学教授(中・東欧史)
1971年生まれ。歴史学者。専門は中・東欧近世・近代史、スロヴァキア史、ハプスブルク帝国史。著書に『近代スロヴァキア国民形成思想史研究』のほか、共編著『王のいる共和政』『ハプスブルク帝国政治文化史』など。2025年4月より朝日新聞書評委員。