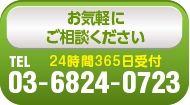聞き手・池田伸壹 朝日新聞 2025/4/1 17:00
関税強化に突き進む米トランプ政権。それを進言した政権ブレーンの一人として注目を集めるのが、米保守派論客でエコノミストのオレン・キャスさんだ。政権幹部や一連の政策に影響を与えながら、自身は政権には入らず、むしろ「重要なのはトランプ後」だとまで言う。その意味とは。真の狙いは、どこにあるのか。
キャス氏とは何者なのか。米国保守の歴史の中で、その思想と特徴はどのように位置づけられるのか。ジャーナリストで思想史研究者の会田弘継さんが、共和党と民主党の状況にも触れながら解説するインタビューも併載しています。
――矢継ぎ早の関税政策などはトランプ大統領個人の思いつきではなく、あなた方は2017~21年の第1次政権の時期からこうした政策を練り、進言していたそうですね。
「その通りです。それが米国にとって唯一の解決策だと考えたからです。経済学者らは当時、米国経済は過去にないほど素晴らしい状況だと言っていましたが、私たちは賛成できませんでした。実際は01年の中国のWTO(世界貿易機関)加盟で、米国の産業基盤は(中国の輸出増などにより)加速度的に弱体化し、限界に達していました」
「それに伴い、私たちの社会も弱体化していました。『絶望死』という現象が典型的です。特に中年の低学歴の白人の間で、薬物やアルコール依存、自殺が増え、平均寿命にまで影響を与える事態になりました。グローバル化の下、米国は若者を海外での戦争に送り、失業と絶望を輸入し、大切な仕事を海外に送ってしまったのです。1980年代の保守の発想は『市場経済と自由貿易』でしたが、いずれも、こうした状況を解決するには有効ではありません。だから関税なのです」
――しかし関税は、米国へ輸出する国だけでなく、物価の上昇などで米国民も苦しめ、誰も幸せにしないのではないでしょうか。
「全く同意しません。短期的には様々な痛みを伴うかもしれませんが、長期的には大きな利益をもたらすと思っています。ひとくちに関税といっても、別々に考えるべき二つの側面がある。一つは交渉のツールとして、もう一つは経済政策としての側面です」
「第2次大戦以降、米国は、関税を交渉のツールとして使うことを基本的に放棄してきました。いま重要なことは、米国が実際に関税を、行使できる力の一形態として使っていることです。そして関税は、経済政策としても理にかなう場合があります。国内で何かを製造することに価値があると信じ、国内産業を保護しようとするなら、効率的な政策手段です」
――国土も狭く、資源にも恵まれていない日本のような国にとって、自由貿易は死活的に重要です。
「日本経済が輸出入に深く依存していることは理解できます。私は、米国と日本はバランスの取れた自由な貿易のパートナーになりうると思っています。これから日米間で、通貨や貿易、産業政策などをめぐる交渉は必要になるでしょう。貿易の不均衡を解決するには、内需が不足しているといった、日本が解決しなければならない問題もあります」
「しかし、ここで注意しておきたいのは、日米を含む自由貿易が成立する領域に、中国は加わっていないだろうということです。これまで保守の常識では、自由貿易は原則推進が『善』とされ、中国のWTO加盟は保守も推進した上で実現しました。ただ米国では、中国が経済的に豊かになれば民主化すると考えていた人も多かったのですが、誤りでした。今後の可能性はゼロとはいえませんが、いま政策を組み立てる際、中国の民主化が近い将来に実現することを前提にするのは誤りでしょう」
――教科書的な話ですが、各国が優位な産業に集中し、自由貿易を行うことでこそ、全体が豊かさを享受できるのではないのですか。
「教科書で習ったアダム・スミスもデイビッド・リカードも、共産党が支配する大国との自由貿易について考える機会はなかったでしょう。中国と自由貿易を行うということは、共産主義の優先順位や政策を、私たちの社会に受け入れるということです」
――かつて、中国の習近平(シーチンピン)国家主席を「素晴らしい友人」と呼んでいたトランプ氏も、そう理解しているのでしょうか。
「今はよく分かっているはずです。またスミスやリカードは、最近の米国のように、モノを買う代わりに何かを売るのではなく、国際基軸通貨ドルで米国債を発行して借金するなどという状態を想定していなかったのではないでしょうか。私たちは、生産よりも消費に偏った米国を変えていこうとしています。そうしたことを一つ一つ解決していく必要があります」
――そうした考えをまとめた2018年のあなたの著作を、ハーバード大学のマイケル・サンデル氏やニューヨーク・タイムズのコラムニストも評価していました。書評で称賛した仏文化人類学者のエマニュエル・トッドさんに最近インタビューしました。米国の社会と経済の現状認識についてはあなたと非常に近い考えでしたが、米国の国内産業の再生については「100年単位の歳月をかければ」と悲観的でした。
「本当ですか? トッド氏と会ったことはなく、フランス語での書評が突然出て、驚きました。色々な見方を共有していると思いますが、産業再生に100年かかるという意見には賛成できません。米国は過去25年ほどで脱工業化が進んだため、基本的には同程度の時間が再生に必要だと考えられます。しかし、そのプロセスを速めることも可能だと信じています。80~90年代にかけて、ホンダやトヨタ自動車などの日本の自動車メーカーが巨額投資をして、短期間で米国工場を稼働させたことを考えてください」
「81年のレーガン政権誕生まで、日本メーカーによる生産はゼロでした。最初は組み立て工場をつくり、やがて部品工場などを含めたサプライチェーン全体が米国に移りました。今では、トヨタとホンダは米国に巨大な研究施設を持っています。結果として、品質低下や価格上昇も起きず、消費者に素晴らしい商品が提供され、何十万もの雇用を生んだのです。これから同じことが半導体でも、さらに速いペースで、さらに大規模に起こると期待しています。生産の自動化も追い風になるでしょう。私はAI(人工知能)が人間に取って代わるとは思っていませんが、あらゆる技術の進歩が米国の産業再生に貢献すると思っています」
――日本製鉄によるUSスチール買収も、米国産業再生の成功例になり得るでしょうか。
「そうは思いません。もし80年代に日本車の洪水のような輸出が問題になっているときに、トヨタがケンタッキー工場を建設するかわりに、伝統あるフォードを買収して近代化するという投資計画を発表したらどうだったでしょう。経済学者が『投資としては同じことだ、何を騒いでいるんだ』と言っても、心理的には大きな違いがでます。間違いなく社会的反発を受けたことでしょう」
今は過渡期、重要なのは「トランプ後」
――ひとくちに保守派といっても、トランプ政権には様々な流れが集結しているようです。あなたは、どのような保守派ですか。
「私たちのグループは、ポピュリズム的な『MAGA(米国を再び偉大に)』運動の一員でも、イーロン・マスク氏に代表されるような、規制緩和や技術革新に関心が高い『テクノ・リバタリアン』でもありません。もちろん、妊娠中絶反対派や宗教右派でもありません。あえて言えば、いずれとも異なる『真正の保守派』です。普通の家族が自立して生活を営む能力、子どもを育てる能力が低下し、地域のコミュニティーが弱くなっていることを、何よりも問題視する保守派です」
「いくら株価が高く、ウォール街やシリコンバレーが繁栄しても、家族やコミュニティーが弱くなってしまっては意味がありません。レーガン政権時代の80年代に確立された(市場経済と自由貿易が善の)保守運動は、東西冷戦期に共産主義と対抗することが最大の課題でした。私たちは、現代の課題に保守がどう対応するかを考えています。格差拡大、労働者と家族、コミュニティーに焦点をあてることが課題です。市場は手段であり目的ではない、という認識も必要です。外交政策についても、2020年代の実際の問題に適用できる保守的なアジェンダを構築することです」
「まだ保守派は雑多な寄り合いで、ビッグバン後の混乱が続いていますが、それが大きな連合となる可能性があると思っています。大きな連合が形成されるとき、それが非常に混乱して見えるのは当然ですが、それは健全なプロセスの一部だと信じています。私の仕事は、保守的な流れをまとめる思想や政策を作り上げることです。私は共和党、そして保守運動を、現代の問題に適応するように変革し、支持基盤を大きくしたいのです」
――それを第2次トランプ政権の任期4年で達成できますか。
「確かに十分とはいえないかもしれませんが、これは過渡期であり、私はトランプ氏を『過渡的な人物』と考えています。彼が非常に得意なのは、これらの全く違うグループを結集させることです。しかし、彼が全く不得意なのは、これらの対立をどのように解決するかを自分の頭で考えることです」
「ただ、4年は、多くの対立を解決するには十分な時間です。重要なのはトランプ後です。これから2028年に向けて、バンス副大統領やルビオ国務長官のような人物が大統領候補としての指名を受ける世界を想像しましょう。次の指導者たちは、『これが新しい保守の連合で、これがそのアジェンダです』と語るのにふさわしい存在になるでしょう。混乱の期間があり、物事が解決され始め、次のリーダーが明確なビジョンを持ち、それを前進させる時期が来ます」
「米大統領選の(党候補者を決める)予備選挙の非常に良い点の一つは、それが解決策を検証するプロセスを提供することです。異なる人々が、それぞれの解決策を掲げて立候補し、競い合うことでしょう。それはすでに始まっているのです」
――あなたは今41歳で、次の大統領候補たちと同世代ですね。
「ルビオ国務長官は少し上、バンス副大統領は1歳下です。これは非常に重要なポイントです。私たちの世代以降は、冷戦もレーガン政権も、歴史の本でしか知りません。この世代が大きな問題として直面してきたのは、冷戦ではなく中国のWTO加盟による問題、イラクとアフガニスタンでの戦争、経済の金融化と金融危機、ビッグテック企業の台頭、薬物中毒、絶望死、パンデミックなどです」
「トーマス・クーンの『科学革命の構造』は日本でも読まれているでしょうか。パラダイムが変わったのです。それに対応する政策が必要です。私は、トランプ政権による政策は長期的には非常に良い結果をもたらすと楽観していますし、トランプ後も(保守政策の流れは)変わらないと信じています」
――トランプ政権の4年間を何とか耐え忍べばいい、という発想では乗り切れないということですか。
「次の世代が権力を持つ世代になるのは、ほぼ自明の理です。それは非常に健康的なことであり、硬直した状態を打破する方法です。クーンが好んで引用したように、ちょっと厳しい言い方ですが『一つの葬儀ごとに進歩する』のです。特に政治においては、選挙で選ばれたリーダーは常に少し遅れた指標です。過去の世代のアイデアに基づいた経歴と実績を築いてきたからです」
「今は、非常に健康的な世代交代が進んでいます。ベビーブーム世代がキャリアの終わりに近づき、もっと現在の課題に関心やつながりを持つ人々が中核に入ってきています。私たちの重視することが主流になることは、もう避けられないでしょう」
――ただ、マスク氏の第2次トランプ政権での動きには批判的ですね。
「マスク氏は、保守的な連合において価値ある役割を果たす可能性のある人物です。彼のビジネスでの成功や民間セクターの力に焦点を当てた姿勢は、共和党支持者一般が求めるものです。しかし、同じ人物が政府機関を効率化し、うまく閉鎖する方法を知っているかは別問題でしょう」
「恒久的な変化」と信じさせるために
――初めて来日し、日本の様々な人と交流や意見交換をして、何を感じていますか。
「正直に言えば、私はトランプ政権の『ショック療法が必要だ』という主張に、より同調しています。なぜなら、最近訪問したカナダもそうでしたが、特に日本で、古いパラダイムや旧モデルへの強い固執を感じたからです。何らかの言葉や行動を駆使すれば、何とか旧モデルを維持できる、と信じている人が多いのです」
「トランプ大統領と、彼の政権で国際交渉に関与する人々も、彼らが試みた対話で、米国の外の世界では思考の変化があまりに少なく、米国の変化が理解されていないと強く認識しています。何が問題で、なぜ変化が必要か理解しておらず、旧モデルを維持することが依然として選択肢の一つだと信じています。新しい方向に進むための第一歩が、もはや旧モデルは選択肢ではないと納得させることだとしたら、その方法を見つける必要がある。これは経済政策の問題というよりも、政治的・心理的な問題です」
――真剣に受け止めていないように感じていると。
「はい。変化が恒久的であると信じるかが、まず大切です。慎重なアプローチを取るほうが信用度を高めることもあるでしょうが、強力に揺さぶるほうが高まる場合もあります。関税政策が実施されたことは、その意味でも非常に重要だと感じています」
==
米保守系シンクタンク「アメリカン・コンパス」のオレン・キャスさん
Oren Cass 1983年米国生まれ。2012年の米大統領選挙で、20代で共和党のミット・ロムニー候補の国内政策ディレクターに。20年に保守系シンクタンク「アメリカン・コンパス」を創設。英フィナンシャル・タイムズや米ニューヨーク・タイムズの定期寄稿者。著書「The Once and Future Worker」(未邦訳)はマイケル・サンデル氏やエマニュエル・トッド氏らに高く評価された。3月に国際交流基金の招きで初来日した。