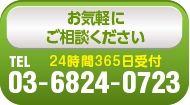余命わずかになったとき死を選べるか 安楽死・尊厳死認める国々と「グレーゾーン」の日本 安楽死「さまよう」日本(1) – 産経ニュース
「母はあれでよかったのかと、今も思います」
川崎市の山口聖子(63)は、2023(令和5)年9月に父の和田恒夫=当時(90)、12月に母の清乃=同(86)=を相次いで見送った。
肺がんを患った父を在宅で看取ったのに対し、難病のパーキンソン病だった母は、寝たきりとなった約3年を特別養護老人ホームで過ごした。そして、飲み下す機能が著しく低下した最後の約半年間は、施設が勧めるような食事量や、積極治療を望んでいなかった。
父母はまだ元気だった18(平成30)年、病気回復の見込みがなくなる終末期に備えて、事前指示書(リビングウイル)を書いた。
「死期を引き延ばすためだけの延命措置は望まない」
父母がきっぱり明示した意志と、二人で対照的な最期。後悔ともつかぬ複雑な思いがわき上がってくる。
施設での母の姿に切なさ
陽気で世話好きだった母は、約10年前にパーキンソン病と診断された。当初は自ら病を知ろうとセミナーに通うなど前向きだったが、18(平成30)年12月、病の影響で転倒、骨折して車いす生活に。さらに、歩けなくなるとの不安から無理に体を動かし、腰椎を圧迫骨折。わずか5カ月で要支援2から最重度の要介護5となった。
施設に入ったのは20(令和2)年7月。病状は徐々に進行していく。「食事の時間がつらい…」。そう漏らしたのは死の半年ほど前だった。
入所時、提出した事前指示書では「口から入るものを、食べられる分だけ食べさせて」と希望していた。しかし、食事の際、「もう食べられない」と職員に伝えても「体力つけるためにもう一口」とスプーンを近づけられる。毎日6種類もの錠剤投薬も同様で、喉につかえたまま通らないような感覚に苦しんでいた。
施設は、母の病状をまだ終末期と捉えておらず、一生懸命世話をしてくれていることは伝わってくる。それでも、面会のたびに切なくなった。
母がいよいよ衰弱したのを見かね、改めて主治医に一切の延命治療を望まない本人の希望を伝え、ようやく了承を得た。母に伝えると、安心したように娘の手をやや強く握り返した。母は翌朝、亡くなった。
「海外ならば安楽死が認められたかも」
2001(平成13)年のオランダを皮切りに、世界では欧米を中心に安楽死を法制化する国が増えた。対して日本では、安楽死はもとより、延命治療を行わず自然な最期を迎える尊厳死も、根拠法は整備されていない。
「父は延命治療を受けず、希望通りの尊厳ある最期を保てたと思うが、母はどうか。もっと早く施設側や主治医と話し合っていたら、死期は早まったかもしれないが、本人は楽だったのでは」
人によって死生観は異なる。聖子にも、親にいつまでも生きていてほしいと願う気持ちは当然あった。他方「母が望んでいたら、海外なら安楽死が認められたかもしれない」との思いもよぎる。
今、身をもって感じている。「終末期であればこそ、本人の希望に寄り添いたい。『尊厳を貫く権利』が制度として選択肢にあることが大事なのではないでしょうか」
「人殺し」と詰め寄られた終末期医療の現場
日本では「死の迎え方」に関する議論がわいては消えてきた。さまようような経緯を振り返りつつ、方向性を考える。
「尊厳ある死とは、本人の望みを最後まで貫き通してあげること。けれど、医療現場は常に法的責任を問われるリスクを考えている」
西日本の総合病院に勤務していた医療従事者は約10年前、終末期の緩和ケアに移行していた肺がん患者の最期をめぐり、家族から「人殺し」と詰め寄られた経験がある。
患者は苦痛を和らげるため医療用麻薬の投与を受けていた。通常は家族の希望で意識を保てる量に抑えていたが、ある日、これまでにないほどの痛みに苦しみ、本人が薬の増量を懇願した。
病院側は家族に電話し、増量によって呼吸停止する可能性があることを説明。了解を得た上で、医師の判断で投薬量を増やした。患者は15分後に亡くなったが、その後駆け付けた家族は「増量に同意していない」と翻意し、法的措置も辞さない構えだったという。
「患者の苦しみようは見ていられないほどで、ほかに選択肢はなかった」。医療従事者はそう振り返る一方、「本人の希望を記した書面があれば、家族との齟齬(そご)は回避できたかもしれない」と悔やんでもいる。
尊厳死、厚労省は事実上容認だが…
日本では、医療処置で意図的に患者の死期を早める安楽死は認められておらず、当事者は刑事責任を問われる。
1991(平成3)年、末期がん患者に致死薬を注射した医師が殺人罪で起訴された東海大病院事件。95(平成7)年の横浜地裁判決は、患者の死期が迫っている▽苦痛緩和の方法を尽くし、ほかに代替手段がない-など、安楽死が例外的に認められる4要件を示したが、医師の行為は要件を満たしていないとして有罪を言い渡した。
他方、患者が望まぬ延命治療を行わない尊厳死は容認されている。厚生労働省は2007(平成19)年、延命治療の不開始・中止を事実上認める指針を公表。ただし、同省は安楽死は対象外と明示した。
尊厳死をめぐり、過去には事件化された例もある。厚労省指針公表の前年に明らかになった富山県の射水市民病院のケースでは、本人や家族の要請で末期がんなどの患者7人の人工呼吸器を外した医師2人が殺人容疑で書類送検されたが、後に不起訴となった。
もっとも、尊厳死容認が広く認知されているとは、今でも言い難い。厚労省が提示するのはあくまで指針であり、法的根拠ではない。可否判断は患者の要請を受ける医療現場に委ねられ、故に医師らはリスク、不安と向き合っている。
法制化求める声の一方、「賛成」は2割
「尊厳死の現状はまさにグレーゾーン。正当性を持たせるためにも法制化は必要だ」。日本尊厳死協会理事長の医師、北村義浩(64)はそう訴え、終末期の延命治療について意志表示しておく事前指示書(リビングウイル)に法的根拠を持たせる方策を提案する。
しかし、「死の迎え方」に関し、積極的に国民的議論が進んでいるとはいえない。
厚労省が22(令和4)年度に行った終末期医療・ケアに関する意識調査では、有効回答(3千人)の69・8%が事前指示書の作成に「賛成」とした一方、法制化に「賛成」としたのは20・4%にとどまった。尊厳死協会が訴えるような、法的根拠の必要性を含む制度への理解が広がっていないことを物語っている。
「尊厳死を望む数は潜在的に多い。希望する最期が確実に実現できるための担保が必要だ」と北村。議論の入り口として、まずは機運醸成が課題となりそうだ。