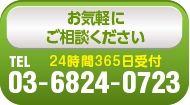緩やかに死が迫る難病ALS、発症31年の男性が感じた「絶望」と「生きる」という選択肢 安楽死「さまよう日本」(3) – 産経ニュース
《こんにちは よく来てくれました》
佐賀市の住宅の一室。ベッドに横たわる中野玄三(70)は、口の形や瞬きなどの「口文字」で意思を伝え、読み上げる介護士を通じて言葉を紡いだ。難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症して、今年で31年になる。
筋肉が徐々にやせて力がなくなっていくALSは、意識ははっきりしているのに体を動かしたり話したりすることができなくなる。進行性で症状が良くなることもない。
人工呼吸器を付けなければ発症から2~5年で死に至るが、装着する患者は全体の約3割にとどまる。多くは自立心や介護による家族の負担への懸念などが理由という。絶望を感じる患者もいて、2019(令和元)年には女性患者=当時(51)=の依頼に応じた医師が薬物を投与したとして、嘱託殺人罪に問われる事件も起きた。
中野も、当初は緩やかに迫る死におびえたが、やがて、病を受け入れて生き抜く道を選んだ。19年前、人工呼吸器を装着。「目が悪くなれば眼鏡をかけるように、僕にとっては、食べて仕事をして、家族との団欒(だんらん)を楽しむために必要な手段でしかなかった」と話す。
進行とともに胃瘻(いろう)を造設するALS患者も少なくないが、中野は自力での食事にこだわる。料理を小さく刻み、前かがみで、おろした山芋とともに喉に流す。今も家族と同じ料理を楽しんでいる。
背中押した言葉 「あなたにはまだ時間が残されている」
最初は小さな違和感だった。地域の運動会で、走り出そうとして後ろ足が地面から離れなかった。その後も異変は続き、何度も検査したが原因がわからない。腕の脱力感など症状は改善せず、焦りと不安から医学書を読みあさり、ALSだと確信した。
発症当時は立ち上げたアパレル会社が軌道に乗り始めたばかり。今後の生活や幼い子供2人の将来を考えると、恐怖で押しつぶされそうだった。
ある日、混み合う駅の階段で突然、脚が震えて動けなくなった。周囲の突き刺さるような視線。「社会に自分の居場所はない」。孤独感、疎外感にもさいなまれた。
絶望から抜け出すきっかけをくれたのは、ある末期がん患者の女性だった。ALSについて話すと、「あなたにはまだ時間が残されているじゃないの」と励まされた。
「動けなくなっても死ぬわけじゃない。家族を残して死ぬわけにはいかない。治らないなら、工夫して乗り越えればいい」。再び生への意欲を沸き起こした。
「それぞれの選択肢があって当然」
終末期の延命治療に関し、日本医師会総合政策研究機構が23(令和5)年、20歳以上を対象に行った意識調査(有効回答1162人)では、71・3%が「行わず、自然にまかせてほしい」と回答。「積極的に受けたい」は3・9%だった。
中野にとり、安楽死や尊厳死は考えたことがなく、賛否もないが、「考えることが悪いわけではない。個々の人生観や価値観に基づき、異なる意見や選択肢があって当然だ」と捉えている。
ただ、自身は誇りを持って生きる道を歩んでいる。病気や障害があっても「諦めるのではなく、何ができるか考える。そうやって試行錯誤してきた」。その経験は、ブログなどを通じて発信。文字の入力やパソコン操作は、わずかに動く左足の親指でマウスを使って行っている。
「僕にとって、生きるとはただ命をつなぐだけではなく、自分の価値観に従って希望を実現すること」。難病であっても自分らしい生活を追求してきた。「生きるという選択肢もある。それぞれの選択が尊重される社会であることが重要だ」