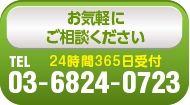タブーなき議論 死期迫ったとき「あらゆる医療を受ける」という親世代はわずか10%未満 安楽死「さまよう」日本(5) – 産経ニュース
「終末期の医療、ケアについて、法的にきちんとしてもらいたいという意見が高まっている。ここらではっきりした方がいいのではないか」
尊厳死の法制化を目指す超党派国会議員約110人でつくる「終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟」。会長の自民党参院議員、山東昭子(82)は、超高齢化に直面する日本での必要性を強調する。
2007(平成19)年5月、厚生労働省が終末期患者の延命治療の不開始・中止を容認するガイドラインを公表。この流れをくみ、議連は12(平成24)年3月、本人意志に基づく延命治療の中止で医師の法的責任は問われないとする尊厳死法案を策定したが、「命の軽視につながりかねない」などと反対の声が根強く、提出を断念した。
尊厳死の根拠法がない中、現場の医師らはリスクを抱えながら従事してきた。患者本人と家族の意見の食い違いに悩むこともしばしばある。
日本財団が20(令和2)年に行った全国調査(有効回答1042人)では、親の死期が迫ったときに重要なこととして「あらゆる医療を受ける」とした子供世代(30~50代)は24・9%だったのに対し、当事者の親世代(60~80代)は9・7%と乖離(かいり)があった。
「全ての人に、プライドを持って穏やかな最期を迎えてもらいたい」と山東。そのための手立てとして、法整備は待ったなしとの立場だ。
4医学会が今年度中のガイドライン見直し目指す
医学界もこれまで能動的に見解を示してきた。
日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本循環器学会の3学会が「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン」を公表したのは14(平成26)年11月。終末期の定義として、生命維持に必須の複数臓器が不可逆的な機能不全となる▽現在の治療を継続しても近いうちに死が予測される-など4要件を明確化し、治療中止などの判断の道筋を示した。
さらに、高齢化の進行や状況の変化を踏まえ、3学会に日本緩和医療学会が加わる形で、ガイドラインの見直しに着手。緩和ケアなど延命治療中止後に必要な措置も包括する形で、25(令和7)年度中の改訂を目指す。
医療現場としては、医師を守る制度ができるのは歓迎の立場だ。ただ、ガイドライン改訂に携わる日本救急医学会会員の医師、渥美生弘(たかひろ)(54)=浜松医大教授=は「法的根拠があると現場としては安心だが、さまざまなケースが想定され、法制化へのハードルは高いのではないか」とみている。
また、医師で立命館大教授(医療社会学)の美馬達哉(59)は「透明性の担保という意味で尊厳死の法制化は一理あるが、生死に関することがマニュアル化される危険性は排除できない」と懸念を示し、「治療について十分説明を受けるなど、まずは患者の権利を守る方策が必要。医師の免責と分けて考えるべきだ」と提案する。
患者にとって最良の選択は何か
一方、京都大教授(生命倫理学)の児玉聡(51)は「法制化されていないが故に、安楽死や自殺幇助(ほうじょ)が認められている国に渡るデスツーリズムや、嘱託殺人のような犯罪への迂回(うかい)路が生じている」と指摘。「耐え難い苦痛から、自ら死を希望せざるを得ない患者の存在を無視してはいけない」と訴える。
児玉が求めるのは、終末期をタブー視しない議論の広がり、そのための環境醸成だ。
「まずは尊厳死を考え、全体像を眺めた上で、安楽死の制度が必要なのかどうか。患者にとって最も良い選択は何か。立場が違っても自己決定権が尊重される社会の形成に向け、議論を始めなければならない」